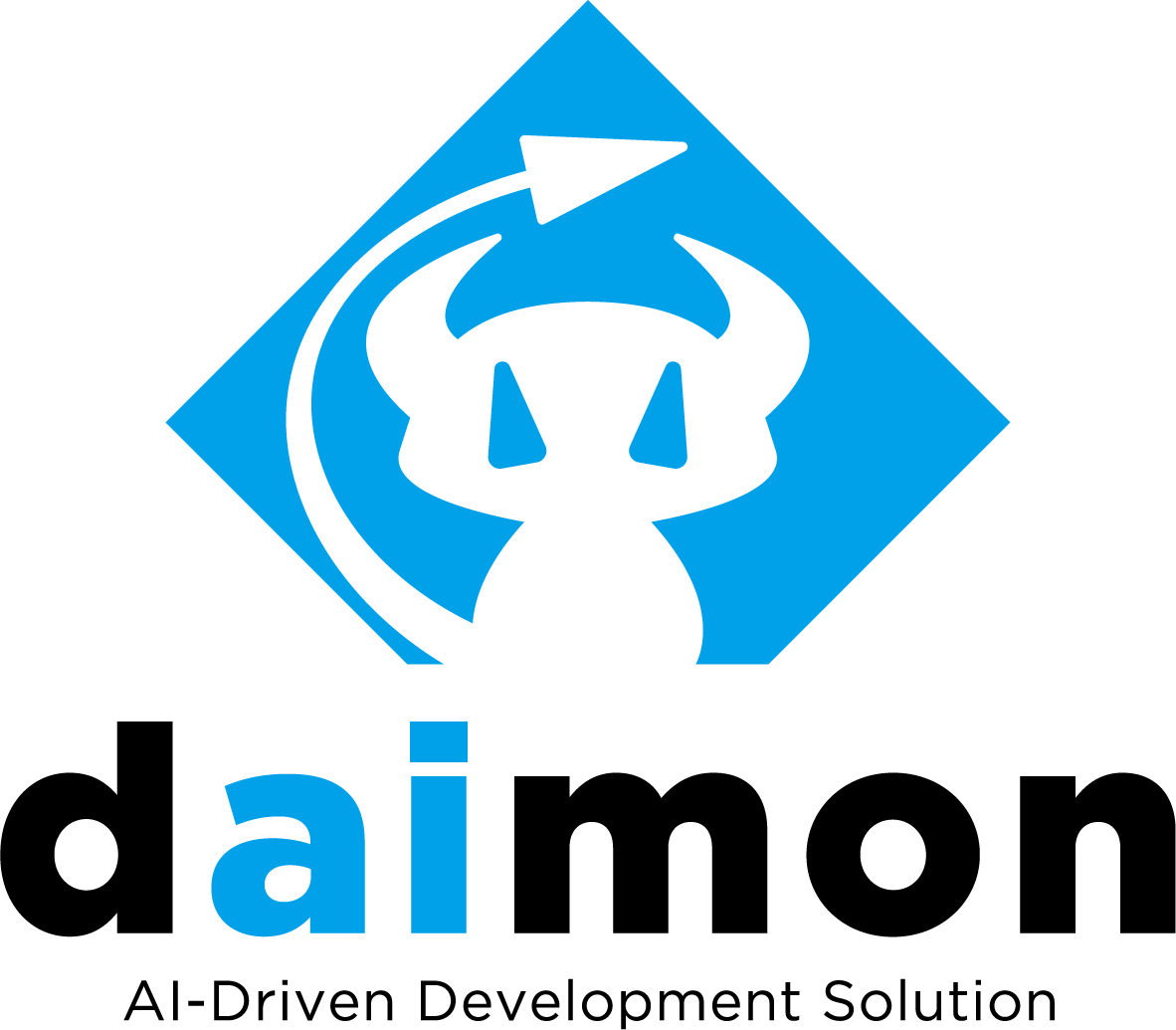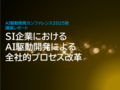スクラム開発から「AI駆動開発ライフサイクル」へ | AI駆動開発カンファレンス2025秋講演レポート
2025年10月30日のAI駆動開発カンファレンスで、「Beyond Scrum AIの力で開発プロセスを変革し続けるチーム」と題したセッションが開催されました。本記事では、KDDIアジャイル開発センター(KAG)の吉田祐樹氏が実践する、AIと人の協働による開発プロセスの進化と、その中で見えてきた課題や学びが紹介され、開発チームのあり方を考えさせられる内容でした。
講演動画はこちら
フィーチャーチームの前提とAI導入の経緯
KAGチームは、全員が幅広い領域をカバーするフィーチャーチームです。エースに依存せず、退職や休暇でも特定領域に穴が開かない体制を築いています。日々モブワークやSlackハドルによるリアルタイム協働、トランクベース開発、独自の休憩ルールなど、実験的な開発文化を持ち、自分たちでルールを選択し続けています。
こうしたチームでAIツール(GitHub CopilotやClaude Codeなど)を導入したことで、開発効率は大きく向上しましたが、リファインメントやバックログ管理の難しさ、ベロシティの不安定化など新たな課題も生まれました。
仕様駆動開発(SDD)への挑戦
AIによる効率化の限界と品質向上を目指し、KAGチームは「仕様駆動開発(SDD)」へ本格的に移行しました。Kiroやcc-sddなどのツールを活用し、スペック(やりたいこと)→使用要件→設計→サブタスク化という流れを明確化。スクラムのリファインメントや計画会議にSDDを組み込むことで、設計や認識合わせを実装前に徹底する体制を築きました。
SDD実践のプロセス
- スペック決定
プロダクトオーナーがAIと壁打ちしながら要件を明確化 - リクワイアメント・ステアリング作成
背景情報や制約、DoD(完了の定義)などを整備 - 設計・タスク分割
Kiroで設計書(design.md)を生成し、レビュー後に実装計画(task.md)を作成。CC-SDDで設計から実装までを連携 - 開発・レビュー
AI支援で実装を進め、人間が品質レビュー。設計段階で技術要素や非機能要件まで徹底議論し、知識共有
SDD導入のメリット
- 実装前に議論・認識合わせができ、チームの知識が揃う
- 着実に前進しているという安心感と、ベイビーステップ的な進捗
- 設計段階で疑問を解消し、AI提案に人間が補足・修正することでより良い設計が生まれる
- 計画・設計に時間はかかるが、実装フェーズが非常にスムーズで全体の開発効率も向上
SDD導入の課題
- 計画会議や設計・タスク分割に多くの時間がかかり、スプリント期間の多くが計画会議で消費される
- バックログのスライスや見積もりが難しく、スプリントとの相性に課題
- 価値ベースで仕様を書くとテスト粒度が大きくなり、API単位の運用が望ましい場面も
- 長時間の会議やレビューで集中力が切れ、レビュー品質が下がるリスク
スクラムとの相性と、新たな手法「AI駆動開発ライフサイクル」
SDD導入により、従来のスクラム(特にスプリント単位の運用)との相性の悪さが明らかになりました。計画会議が長期化し、スプリントの大半が計画で消費されるため、KAGチームではスクラムから一歩踏み出し、AI駆動開発ライフサイクル(AI-DLC / AI-Driven Life Cycle)への関心を強めています。
AI-DLCではスプリントではなく「ボルト」単位で開発を区切り、短サイクルで設計・実装・テスト・振り返りを繰り返します。AIが計画・実装を主導し、人間は監督や意思決定、レビューに注力することで、柔軟かつ効率的な開発サイクルを目指しています。
今後の展望と学び
- AIエージェント活用による技術力の変化を実感。コーディング力低下の懸念もあるが、設計や議論で知見が深まる
- ドメイン駆動設計(DDD)や設計技法の習得など、AI時代ならではのスキルアップにも期待
- モブワークやAIコーディングだけではジュニア育成が難しい面も。仕様駆動開発や設計の議論を通じた学びの強化が必要
講演を聞いて感じたこと
SDD導入により設計・品質・知識共有が飛躍的に向上する一方、計画会議の長期化やスプリントとの相性など新たな課題も明確になりました。スクラム・SDD・AI-DLCなど最適な手法を柔軟に選択し続ける姿勢が、AI時代の開発現場には求められています。AI活用による開発プロセス変革は、現場の試行錯誤とチームの対話から進化していくことは間違いなく、AIツールの選択に加え、チームの特性や開発プロダクトの相性との見極めが重要になってくると感じました。
JTPの登壇講演レポートはこちらから
AI駆動開発ソリューション daimon
AI駆動開発ソリューション「daimon」は、AI活用の導入から現場への定着まで、お客様の開発組織に寄り添い伴走することを重視した新しいサービスです。AI-Driven Development(開発支援)、AI-Driven Support(導入・改革支援)、AI-Driven Optimization(最適化支援)の3つのメニューを軸に、実践的かつ柔軟にご支援します。単なるツール導入ではなく、「どこにAIを使うのか」「誰がどこまで責任を持つか」「どの指標を見て運用するか」といったルール設計と現場定着までトータルでサポートし、お客様ごとに最適なAI駆動開発を設計し、課題解決まで伴走します。
詳細は下記のサイトをご覧ください!