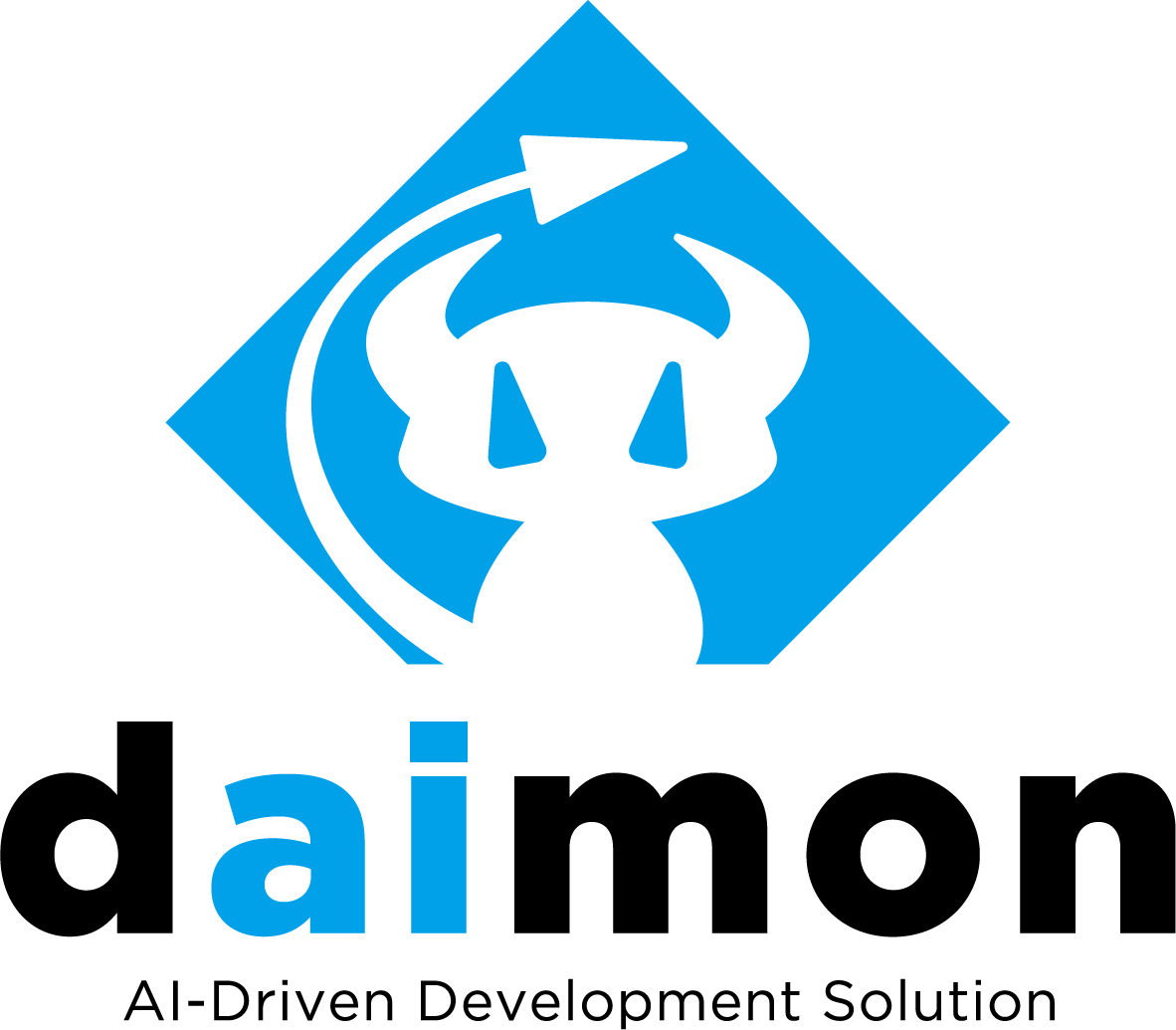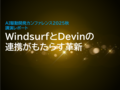「AIを育てる」―人とAIが共に品質を高める開発現場 | AI駆動開発カンファレンス2025秋講演レポート
AI駆動開発カンファレンス2025秋にて、ネクストスケープ社によるセッション、「AIをチームメンバーに育てる ─コンテキストを共有する開発環境づくり」が開催されました。実際の大規模プロジェクト現場でのAI活用の工夫や、直面した課題、さらにそれを乗り越えるための具体的な解決策など、ぜひ取り入れたい内容が多く紹介されました。本記事では、そのレポートをお届けします。
講演動画はこちら
AI駆動開発への挑戦
取り上げられたのは、企業向けデジタルプラットフォーム開発プロジェクト。要件定義や設計・一部実装を他ベンダーが担当し、2025年4月からNEXTSCAPE社と親会社が参画。AI駆動開発を初めて本格導入した大規模案件で、参加人数は20〜30名にものぼりました。
特徴的だったのは、Excel仕様書や一部フロントエンドコードの引継ぎ資産があったこと、そしてCursorやChatGPT、CopilotなどのAIツールを積極的に活用した点です。プロジェクトに合わせてcursorrulesをカスタマイズし、Microsoft AzureやAzure DevOpsを活用し、単一のGitリポジトリでコード管理を行う体制が構築されました。
AIを活かすための現場の工夫と課題
AIを「チームメンバー」として機能させるために、現場ではさまざまな工夫が重ねられました。まず、クラウド知識やプロジェクト情報をAIに学習させ、業務理解を深めることからスタート。cursorrulesやCopilot Instructionsの編集・カスタマイズによって、プロジェクトに即したAI指示が作成されています。
具体的には、次の取り組みが行われました。
- 引継ぎ仕様書(Excel)をSharePointコネクタ経由でChatGPTに読み込ませ、マークダウン化してcursorに渡し、実装を進める流れを構築
- Azure DevOpsやMCPサーバーからプロジェクト情報やチケット仕様をAIに読ませ、シークエンシャルシンキングやメモリー機能を活用して、段階的な実装やコンテキスト管理を工夫
実践の中では、いくつもの課題も明らかになりました。AI成果物の品質は人間によるチェックが不可欠であり、テクノロジー基礎力や応用力がないとAIを使いこなせない場面も多いとのこと。大規模案件ではメンバーのバックグラウンドが多様なため、AI活用の浸透や品質担保が難しくなります。また、ツールの進化が早く、cursorrulesのメンテナンスやバグ対応が継続的に必要となり、「AIがそう言っていた」だけでは、説明責任を果たせない場面も多々発生しました。
取り組み後の具体的な事例
ここまでの取り組みや課題から、「AIは単なるツールではなく、環境や人との関係性の中で成長させていく必要がある」「AIの活用方法はプロジェクトの状況やフェーズによって最適解が異なる」といった学びが得られています。
こうした知見を踏まえ、AI導入のシナリオごとに解決策が模索された事例も紹介されています。
①新規プロジェクトでのAI導入
プロジェクト開始時からAIエージェントの役割や専門性を計画し、AIが読める仕様書(AIフレンドリーなドキュメント)を整備。AIエージェントの配置計画やガードレール(アクセス制限)も設計。MCPサーバーやClaude Codeを活用し、情報アクセスやサブエージェント定義で効率化を図るなど、現場での工夫が重ねられました。また、コード生成AIとレビューAIに異なるLLMを使うことで、アウトプットの品質向上も実現しています。
②既存プロジェクトへのAI導入
既存資産のドキュメントやコードをAIが読める形に順次変換。コード解析ツールやMCPサーバーを用いてドキュメント化を推進し、AIエージェントの配置計画を立てて段階的に範囲を拡大。まずは小さな範囲からAI活用を始め、既存コードや仕様との整合性を確認しながら徐々に拡張していくアプローチが取られました。
さらに、AI成果物の信頼性やレビュー設計、品質とスピードのバランスも課題となります。人が書いてもAIが書いても間違いは起こるため、リスクベースでレビュー・テスト範囲を設定。絶対に失敗できない処理は人が確認し、それ以外はAIやテストで担保するなど、線引きを明確にした事例も語られました。
これからのAI駆動開発に求められること
セッションの締めくくりでは、「AIは導入しただけで活躍するツールではなく、育てるもの」であるというメッセージが強調されました。
AIが活躍できる環境やドキュメント、プロセスを整備し、変化や進化を受け入れながら、AIも人も常に成長させていく姿勢が重要です。現場ごとにノウハウやツールをテーラリングし、チーム全体で品質を担保しながらAI駆動開発を推進することが、これからの開発現場に求められているとまとめられました。
セッションを聞いて
このセッションを聞いて、事例を交えた具体的な取り組みに加え、「AIを活用していく上での距離感」など、マインド面での学びを多く得ることができました。「AIは万能ではない、AIは上手く使うものである」といったことを常に根底に置きながら、効率第一ではなく、品質を第一に考えたAI活用が非常に大切であるということを忘れてはいけません。
JTPの登壇講演レポートはこちらから
AI駆動開発ソリューション daimon
AI駆動開発ソリューション「daimon」は、AI活用の導入から現場への定着まで、お客様の開発組織に寄り添い伴走することを重視した新しいサービスです。AI-Driven Development(開発支援)、AI-Driven Support(導入・改革支援)、AI-Driven Optimization(最適化支援)の3つのメニューを軸に、実践的かつ柔軟にご支援します。単なるツール導入ではなく、「どこにAIを使うのか」「誰がどこまで責任を持つか」「どの指標を見て運用するか」といったルール設計と現場定着までトータルでサポートし、お客様ごとに最適なAI駆動開発を設計し、課題解決まで伴走します。
詳細は下記のサイトをご覧ください!